ケーススタディー: クリスプ様

クリスプ・サラダワークス、医療従事者らにサラダを無償提供
「最前線で働く医療現場を支援」
店舗デジタル化で顧客体験の向上を
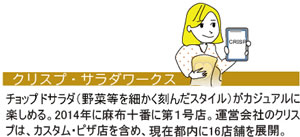
飲食業を20年近くやってきて、この仕事はお客様を笑顔にできるということが一番の魅力で素敵な部分だと思っています。仕事終わりに、ご飯を食べたり、1杯のコーヒーを飲んだりするだけでも、あるいは、店員さんとちょっと会話するだけでもハッピーになれることがありますよね。
クリスプは緊急事態宣言が出て以降、臨時休業しましたが、多くの人が不安に駆られるなか、コロナと最前線で闘っているのが医療従事者です。医療現場で働いている方を少しでも笑顔にできればと考えました。
この取り組みを始めたのは、私の原体験も大きいですね。私は高校生の時に渡米し、2001年の「9・11」を体験して米国が一つになる様子を目の当たりにしました。飲食店では、軍や警察などの最前線で働いている人に対して、コーヒーを無料で出すといったことは当たり前の光景でした。有事の際、飲食店として何ができるか考えたときに、医療従事者をフォローするという考えが自然と出てきたのです。

どのくらいの病院に、どのくらいの数のサラダを提供するといった、ゴールが明確にあるわけではありません。支援は3月下旬にスタートしたのですが、当初は医療関係の方がお店に来てくださったら無償でサラダをお渡ししていました。反響が予想以上に大きくて、ご丁寧に手紙までくださる方もいて……感染者病棟に勤務する看護師さんからは「現場では緊張感に押しつぶされそうですが、応援してくれる人がいることを知って温かい気持ちにちになりました」という嬉しい言葉をいただきました。
6日間で2,296食(「R PIZZA」での無償提供を含む)と大変多くの方にご利用いただきました。ただ、最前線で新型コロナウイルスと闘う医療関係者の中には、注文をしても忙しくて店舗でピックアップをすることができない方も多く、「医療現場に直接届けてほしい」という意見を多くいただきました。
また、同時に私たちの活動をサポートしたいという多くの方の声もいただき、「CRISP CONNECT」というプロジェクトを立ち上げました。多くの方のご協力と寄付を得ながら、サポートメンバーと一緒になって都内・神奈川県東部などの医療現場にサラダを無償提供・配達を行っています。5月22日時点で医療機関へ15,000食を超えるサラダをお届けすることができました。
クラウドファンディングを通じた寄付のアイデアも初めはありませんでした。私たち以外にも「何かしたい」と思っている人が多いですね。自分たちだけでやるのではなくて、みんなでやることで、大きな善意の輪が広がっていきます。物理的な支援以外にも、応援メッセージという形でもいいと思うのです。支援する側もポジティブになることができる場をつくりたかったのです。
支援している病院名については、センシティブな問題もあり、基本的には開示を望まれている病院以外は公表していません。本当に大変な状況で働いていらっしゃる医療従事者の方に余計な負担をかけたくないという思いがあります。

課題は多いのですが……。クリスプに「スピーディーに動ける文化」がすでに根付いていたというのはあります。緊急時というのは、緊急時になってはじめて動こうと思ってもできません。平時から速い判断を心掛けてきたことがよかったのだと思います。
それと、青臭いかもしれませんが、私は「会社は世の中に価値を与えていくものだ」と考えています。売り上げも大事ですが、現在のような状況下で、いったい自分はどうしてこの会社をやっているのかと考えました。すると、何が起こるかわからないときに今を守ることは必要ない、やっぱり「人を笑顔にしたい」という強い思いをあらためて確認しました。
マーケティングの世界で「N1分析」という言葉があります。顧客1人の分析から事業は成長するというものです。みんながいいというお店ではなくて、「このお店がなかったら生き甲斐がなくなってしまう」というお客様が1人いれば十分だと私は思っています。
リピーターとファンは違うのです。ひいきの野球チームがあるとします。球場から遠くてなかなか観戦に行くことができないけれど、周りの人に「このチームが大好きだ」「こんなところがいいんだ」と熱く語ってくれる人、応援してくれる人を増やしていきたいとずっと思っています。
お金をどれだけ落としてくれるか、来店頻度はどのくらいあるか、そういうことはあまり関係ありません。熱く応援してくれるファンを私は大切にしていきたいですね。
私たちはブランディングやマーケティングのプロ集団ではありません。クリスプの前に立ち上げたお店でのことですが、こんな経験がありました。来店回数が一定数に達すると1回のお食事が無料になるスタンプカードを発行しており、頻繁に来てくれる、あるアメリカ人のお客様にスタンプカードのご利用を勧めたところ、お客様はこうおっしゃるのですね。「私はこの店が大好きだから、無料券は自分で使わずに、友達にプレゼントするんだ」と。反省しました。「このお客様のお店が好きという気持ちに応えていないのではないか」と思いました。
割り引きではなくて、例えば、チョコレートにスタッフの思いを書いた付箋を貼ってプレゼントするだけでもいいんです。感謝の気持ちを伝えることが大事ではないか。「熱狂的なファンをつくる」と掲げているのなら、そういった細やかなことに気づいて行動できるスタッフがいるお店づくり、その積み重ねがブランディングなのだと考えます。
おっしゃる通りです。いい飲食店は3つ要素があるといわれています。まずは「味」、それからスタッフの「人」、業態や内装といった「箱」です。インターネットがこれだけ普及してきて、消費者のニーズも多様化していくなかで、おいしいのは当たり前、お店のデザインもそれだけでは決定的な成功要因たりえない時代になりました。だとすると、お客様が何を求めて飲食店に足を運ぶのか。飲食店の価値は今後、「顧客体験」になってくると私は考えています。つまりは「人」なのです。
スタッフから「夜遅くまでお疲れ様です」とひと言声をかけられたら、少しうれしいじゃないですか。そういった言葉は、機械やロボットから発せられるよりも心に響くと思います。お客様にとってよりよい体験ということを考えたときに、注文の部分はデジタル化して、その分スタッフにはお客様とコミュニケーションを図ってもらいたいと思うのです。私たちが考えるデジタル化は、効率化や無人化というよりも、よりよい顧客体験のための「余白」の創出かもしれませんね。
記事を通じて、みなさんの支援の思いと善意の輪がさらに広がっていけば、これほどうれしいことはありません。メディアプラットフォーム「note」やSNSに私が書いたメッセージに共感してくださった方からの反響がすごく多いですね。
テレビやラジオといった既存のメディアはある意味、一方通行の発信でしたが、SNSでは双方向のコミュニケーションができるようになりました。オーディエンス同士がつながってコミュニケーションができるのもSNSの特長です。広報では既存のメディアと新しいメディアを使い分けていると思いますが、私自身は「すべてつながっている」という前提でブログを書いたりSNSで発信したりしています。
飲食業界はもうコロナ以前の状態に戻らないと思っています。私たちがコロナ以前にモバイルオーダーアプリ、セルフレジの導入とデジタル化を実現できたのは幸運でした。コロナがいつ終息するのか全く予想がつかない今、嵐の中で、どうやったら外に出ていけるのか、どんな装備をすべきかを考えるべきではないでしょうか。
これまでの飲食店は、店舗に来てくださるお客様に商品を提供するのが当たり前でしたが、今はモバイルアプリで注文して好きなときに取りに来るピックアップやお客様の家に商品をお届けするデリバリーが当たり前となっています。店舗という「箱」の中だけにいては考えつかないようなサービスが出てきているのです。
今も苦しんでいる業界の仲間が多いので、軽々しくは言えませんが、嵐をただ過ぎ去るのを待つだけでいいのでしょうか。今までの成功体験や売り上げをいったん脇に置いて、ピンチをチャンスに変えるチャレンジが必要です。自分にも言えることですが、今一番必要なことはしっかりとした装備で外に出ていくことだと強く思うのです。
外出自粛要請を受け、インタビューは4月末にテレビ会議システム「Zoom」で行った。画面越しにも伝わってきた宮野社長の“熱”。それは従業員にも伝わっていくようだ。臨時休業中(現在は全店舗で営業中)の店舗のうち4店舗を医療関係者のためのサラダを作る拠点として稼働。緊急事態宣言発令中は「従業員には給与を保障しました。出勤可能なスタッフがボランティアという形で出てくれています。できる範囲で続けていきたい」と宮野社長は語る。
※文章や画像の転載・転用はご遠慮ください。
