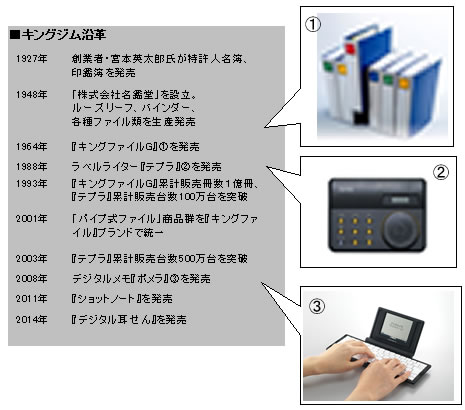ケーススタディー: キングジム様 (2014年11月号掲載)
※文章や画像の転載・転用はご遠慮ください。
 キングジム
キングジム
広報室
稲葉大力氏
SNSでの見せ方工夫、ファンつかむ
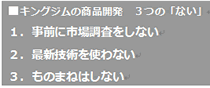
当社の開発本部は『テプラ』を中心に扱う部隊、新規概念商品の企画開発をする部隊、ファイルなどのステーショナリー系の開発を中心とした部隊などに分かれていますが、ファイルのグループがデジタル文具を企画開発しても構わないし、課をまたいで共同で開発するのも自由です。
「世の中にないものを出す」ということを前提として商品開発をしていますから、他社のものまねはしません。また、事前に市場調査を行いません。これまで世の中にない商品を世に出すのだから商品を出してみなければ売れるかどうか分からないという考えからです。
開発本部では開発本部長と前本部長(現専務取締役)が隣り合わせに座っていますが、その前にパイプいすが置いてあります。このパイプいすを舞台に繰り広げられる議論が商品化を左右する場となっています。開発のメンバーがそこに「こんなのはどうですかね」と意見を求めにやってくればプレゼンの始まりです。
企画書は形式が決まっているわけでなく、資料を持参せず口頭で説明するメンバーもいたりとさまざまです。本部長が「これでやってみたら」となってはじめて社長を含め、役員を前にした開発会議に進みます。
実際のところ、開発会議は社長曰く「約9割の提案を承認する場」となっているため、開発本部長のOKをもらうことがかなり重要となります。
『ポメラ』が現在のこうした開発スタイルの起点となっています。
『ポメラ』では大学教授をしている社外取締役が1人だけ「こんな商品を待っていた」と賛成に回り、「1人でもこれだけこの商品を欲しいと思っている人がいるなら出してみたらどうか」と社長のゴーが出ました。
蓋を開けてみれば想定外の大ヒットで、開発担当者は雑誌やテレビの取材を受けたり、社長賞を受賞したりして一躍ヒーローになりました。こうしたことが開発部門の中でかなりの刺激になったようで、「次は私が」という意欲が高まってきたのは確かですね。
厚型ファイルなど法人向け商品の市場が飽和状態となっているので、一般コンシューマー向けの商品開発にも力を入れているところです。
ノートで言えば、当社が普通のノートを出しても先発メーカーには勝てません。手書きメモをデジタル化できる『ショットノート』のような用途を限定したものや機能的に付加価値が付いた商品を出そうと企画開発に取り組んでいます。
広報がかかわるのは、開発からこんな商品が出るという話がきた段階からです。どんなコミュニケーションをしようか、どんな見せ方があるのかアイデアを練り始めます。
当社の広報はコミュニケーション全般を扱っており、ホームページ(HP)、販促物の一部、広告についても広報の業務になります。
メディアに対しては担当を設けていませんので、上長含めて7人全員での対応となります。広報の成果としてメディアに取りあげてもらうことを重視しています。対応にはスピード感が求められるため、全商品について全員が説明できるよう情報を共有しています。
 『デジタル耳せん』
『デジタル耳せん』
騒音だけをカットして人の声は聞こえ、2014年上半期の日経MJ「ヒット商品番付」にもランクインした人気商品
『デジタル耳せん』といっても、商品名だけではどんな商品なのか分かりません。どのような効果があるのか、それが分かっていただければ商品への反応がよくなるのではと考えました。そこでサンプル音源を紹介するプロモーションビデオを制作し、HPに取り込みました。
この商品にはノイズキャンセリング技術が用いられていますが、この技術は既に市場に出回っていて当社が開発した技術ではありません。その技術を流用して異なる用途で使うという発想の転換が面白かったのではないかと思います。
それと大きかったのがネーミングです。「ノイズキャンセリング」という言葉にこだわらず、わかりやすく『デジタル耳せん』としました。「耳せん」という言葉をとっかかりにして「どんな商品だろう」と思っていただけたようです。
また品番も「MM1000 シロ」と、これも「ミミセン」と読めます。これは当社から言ってはいませんが「“ミミセンしろ”という意味ですよね」というツッコミがSNS上であり、それも話題になりました。ちなみにこれは偶然ですが(笑)。
大企業では、あまり自由に商品開発をすることができません。大企業からの転職組であった開発担当者は、当社の自由に商品開発できる風土を存分に活用し、『デジタル耳せん』を開発しました。本人も自由な発想で商品開発をしたいという思いがあり、転職を決意したそうです。
ひとつのエピソードとして、実際に市販されているノイズキャンセリングイヤホンのイヤホンジャックの部分を切り離すと、それが「デジタル耳せん」になるんです。それを彼が試作品としてプレゼンしているのを見てユニークだなと思いましたね。
リリースでは次の3点を心掛けています。あまり長くならないようにする。要点をまとめる。シンプルなタイトルにする。
『デジタル耳せん』では「周囲の騒音を約90%カットしながらも、人の呼びかけ声は聞こえる」というキャッチコピーをつけました。本文でも製品特長を箇条書きにして端的に整理しました。
それと、できるだけイメージをわかりやすく説明することが大切です。「300Hz以下の騒音を約90%カット」と言葉だけで説明しないで、環境騒音の波形と、逆向きの波長を出して互いに打ち消し合うといった図解を入れ、ノイズキャンセリング技術をより理解しやすいよう工夫しました。
SNSではコミュニケーションを重視しています。ツイッター、フェイスブックの担当者はそれぞれ1人で更新しています。担当者は発信だけでなく双方向のやりとりを意識しながら、消費者の印象に残るようなビジュアルや言葉選びを心掛けています。あの「オフトゥン」がそうでした。
 『着る布団&エアーマット』がツイッターで話題に
『着る布団&エアーマット』がツイッターで話題に
ツイッターでのPRがあったので、「単なる防災用品」で終わらずに、あれだけの反響を呼んだのだと思います。
当社は、おなじみの『キングファイル』だけでなく、オフィス環境改善用品として、天井の空調機に取り付けて空調効率をよくする『ハイブリッド・ファン』シリーズなども販売しています。『着る布団&エアーマット』もそうしたBtoB向け商品という位置付けになります。
ファイルメーカーなのでファイル同様、パッケージを棚に収納できるサイズにしました。『着る布団&エアーマット』はオフィスで余震が来てもぱっと動けるような、ヒト形で着るタイプの寝袋です。
フェイスブックでは普段当社になじみのない方もすんなり入ってきてもらえるよう、毎月2回ほど、商品情報以外の季節や最近の出来事を投稿するようにしています。コメントにこまめに返信することも意識してやっていますね。
商品化までの苦労など一番その商品ついて語れるのが開発担当者です。
当社の商品開発では最初に提案した者が最初から最後までその商品の面倒をみます。もちろん途中、サポートがつきますが、工場に出向き生産ラインを見たり、現場と交渉したりするのも開発担当者の仕事になります。内容的にも開発者が商品について語るのが最も面白いと広報では考えています。
社長の宮本のいう「9割三振でいい。1割でホームランを打て」というチャレンジの姿勢が社内に浸透してきました。
失敗から学ぶという社風やトップに注目をいただいていることは大変ありがたいと思っています。年間20−30の新商品をリリースしていますが、商品も多岐にわたっていて、ターゲットもさまざまです。どう商品をPRしたら効果的なのか悩ましいとはいえ、そこがまた広報としてのやりがいでもあります。
今年6月に、デジタル名刺ホルダー『メックル』、デジタル名刺ボックス『ビズレージ』の新商品2モデルと2010年発売の名刺管理機器『ピットレック』とを合わせて、デジタル名刺関連商品の発表会を行いました。当社はリリースのみの発表が多いですが、発表する商品・サービスによってはこのように発表会を開いてPRすることがあります。
SNSを含め、ウェブを活用したPR方法についてはまだできることはたくさんあると考えています。より話題になるようなコンテンツづくり、一例を挙げるとネットを通じて拡散していくような動画づくりに今後は取り組んでいきたいと思っています。