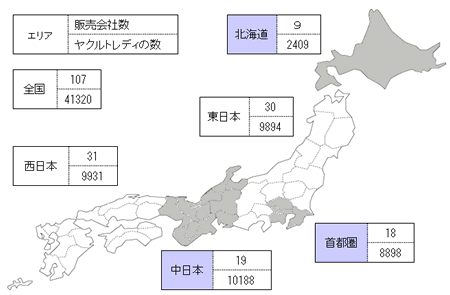ケーススタディー: ヤクルト本社様 (2012年9月号掲載)
 ヤクルト本社
ヤクルト本社
広報室
CSR・環境推進室 課長
吉田直之氏
「愛の訪問活動」が40年に
この活動は、1972年に福島県郡山市のヤクルトレディが、自分の担当地域の中で独り暮らしのお年寄りが誰にも看取られずに亡くなったという新聞記事を見て心を痛め、独り暮らしのお年寄りに自費で『ヤクルト』を配り始めたことがきっかけです。
その後、販売会社や民生委員等がこの活動に共鳴し、さらに自治体も動かし、全国に活動の輪が広がっていきました。2012年3月の時点で、全国147の自治体と連携し、3500人を超えるヤクルトレディが約4万7000人のお年寄りのお宅を訪問しています。
地区や自治体との契約内容によって異なりますが、基本的には自治体から対象となるお年寄りをご紹介いただくとともに商品の代金を負担していただき、週3回程度その方のお宅を訪問します。
ヤクルトの商品を届けると同時にご様子を伺い、お会いできない家については新聞がたまっていないかなどに注意し、安否の確認が取れない場合には販売会社のセンター(営業所)を通じて自治体に連絡するという流れで行っています。
また、毎年9月中旬には敬老の日のお祝いとして「メッセージを添えたお花(カーネーション)」をプレゼントしています。「敬老の日 お花プレゼント」は2005年の創業70周年記念企画として実施したのが始まりで、今年で8年目を迎えます。お花を贈られたお年寄りにも、お渡しするヤクルトレディにも大変喜ばれていることから、継続して実施しています。
 「愛の訪問活動」の様子
「愛の訪問活動」の様子
具合が悪くて倒れていたところに遭遇した、ガス漏れを発見したなどという事例は数多くあります。日常的に訪問していると普段との違いに気づきやすくなるのでしょう。
「ヤクルトレディさんが気づいてくれたから無事病院にいくことができた」などという話もたくさん聞き、この活動が実際に役立っていると感じられます。
この活動はボランティア関係者や行政の福祉担当者からも高い評価を受け、(財)経済広報センターの「優秀企業広報特別賞」(平成3年)や「厚生大臣表彰」(平成6年)をいただきました。
ヤクルトレディは地域に密着して、地域の隅々まで回っているというイメージがあると思うのですが、そうしたビジネススタイルの特徴を生かして、地域の安全・安心に協力しています。
・不審者を発見したら通報する
・犯罪への注意を促すチラシを配布する
・センターに「子ども110番」のステッカーを掲げて子どもたちの避難場所にする
・お届けの際に「安全パトロール」のステッカーをつけてパトロールする
など様々な取り組みがあります。
「愛の訪問活動」が認識されるようになって、活動が戸別から地域へと形を変えたものとも言えます。2012年3月現在、各地の警察署等327団体と提携し、79の販売会社、1300センター、約2万人のヤクルトレディが協力しています。
地方紙を中心に「愛の訪問活動」や「防犯協力活動」が取りあげられることは多いです。「敬老の日 お花プレゼント」は30〜40社の媒体に取りあげられました。
また最近では3月に、埼玉県の入間市で孤立死しそうだった男性がヤクルトレディに助け出されたニュースが全国紙で掲載されました。ポストに新聞がたまっていて応答がないのを不審に思ったヤクルトレディが警察に通報したことがきっかけでした。
ほかにも北海道の室蘭で事故を未然に防いだことが報道されたり、最近孤独死の問題も深刻化していることから、マスコミからの問い合わせも増えているようです。
ヤクルトの広報室は、CSR・環境推進室、IR室、消費者班、広報班、学術・編集班に分かれています。
消費者班は国内5支店に設置しているお客様相談センターの統括、広報班はメディア対応、学術・編集班は社内外向け広報誌の発行や乳酸菌に関する学術情報の収集・発信を主に担当しています。
学術広報活動では、乳酸菌が持っている有効性などに関する研究結果や知見を、研究会やシンポジウムの開催を通じて情報発信しています。広報の中で学術情報を専門に担当する部署があるのは珍しいかもしれません。
当社はエビデンスや知見に基づいて、人々の健康に貢献したいと考えています。会社の成り立ちにもつながりますが、創始者である代田稔博士が研究した「乳酸菌 シロタ株」は、毎日飲むことにより人々の健康に役立ててもらうことを願って世に出されました。
この精神が脈々と受け継がれ、当社の事業の基本となっています。広報セクションもそれに沿って活動しています。